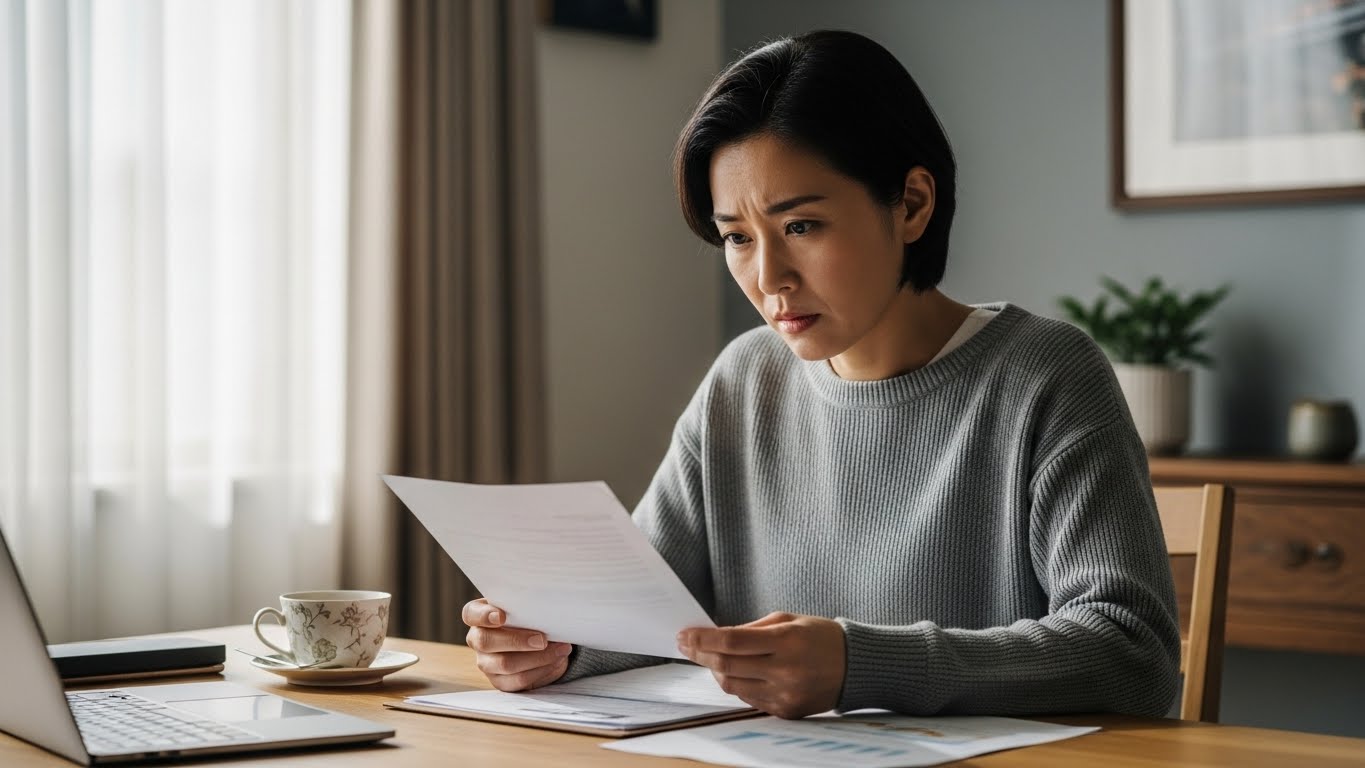運送業の許可は貨物自動車運送事業法に基づき、国土交通大臣から取得する必要があります。5年ごとの許可更新制度が導入されるほか、契約の書面交付義務、実運送体制記録簿の作成義務化など、物流事業者の取引適正化・透明性向上を目的とした規制が強化されてきています。
「貨物自動車運送事業法」の目的
・貨物自動車運送事業の運営を、適正かつ合理的にすること
・民間団体等においての自主的活動の促進により、輸送の安全を確保すること
・貨物自動車運送事業の健全な発達を図ること
→以上を達成することで、公共の福祉の増進に資することを目的としています。
運送事業の種類
「貨物運送事業」
・一般貨物自動車運送事業
有償で自動車を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以 外のもの
・特定貨物自動車運送事業
特定の者(特定の荷主)の需要に応じて、有償で自動車を使用して貨物を運送する事業
・貨物軽自動車運送事業
有償で軽自動車を使用して貨物を運送する事業
→通信販売事業者からの請負配達、飲食店からの請負宅配などが該当します
・貨物利用運送事業
自社では車両等を持たず、他の実運送会社を利用して貨物の運送を行う事業
「旅客運送事業」
・一般貸切旅客自動車運送事業
定員11名以上の自動車を貸し切って旅客を運送する事業
→貸切バス、ツアーバスが該当します。
・一般乗合旅客自動車運送事業
乗合旅客を運送する事業
→日常での通勤、通学で利用する公共の乗合バスが該当します。
・一般乗用旅客自動車運送事業
定員11名未満の自動車を貸し切って旅客を運送する事業
→タクシー、ハイヤーがこれに該当します。
・特定旅客自動車運送事業
特定の者の需要に応じて、一定の範囲の旅客を運送する事業
→特定の事業所の通勤バス、スクールバス等がこれに該当します。
一般貨物運送事業の許可要件について
運送事業の種類を問わず、共通する要件として、「営業所・休憩室・車庫地があること」が求められます。(車両の所有を伴わない「貨物利用運送事業」は不要です)
今回は、「一般貨物運送事業」の許可取得要件について、まとめてゆきます。
「車両が5台以上あること」
・用途が貨物の車両であることが求められます。軽トラックは不可
・資金が潤沢であれば問題ないのですが、手形決済・リース中の車両等が多くなると、事業の運転資金計画上で、資金不足に陥ってしまうことがあります
「営業所・駐車場が確保されていること」
・営業所は、建築確認を受けた建物でなければNGです。(✖仮設のプレハブ等)
・駐車場は市街化調整区域であればOKです。まれに農地にむりやり駐車場を設定しようと頑張る事業者さんもいるようですが、それはありえません
・営業所と駐車場間が、直線距離で5キロメートル以内である必要があります。
→営業所が札幌にある場合は、特例で10キロメートル以内に緩和されています。
「必要人数の資格保持者が確保されていること」
・「運行管理者」と「整備管理者」を確保しなければなりません
→「整備管理者資格」を持っていない方でも、2年以上整備管理の経験があって、整備管理者選任前研修が受講済みであれば認められます。
「運転者の人数が車両台数分以上であること」
・社長(事業主)も人数にカウントできますが、運行管理者は運転者としてカウントすることはできません。
「必要な資金が確保できていること」
・事業を行うにあたり、6か月分の運転資金があることが条件になっています。ただし、車両のリース料や建物・土地の賃借料は、1年分用意しなければなりません。
「社会保険に加入していること」
・強制加入なので必須です
行政書士にご確認を
許可の要否、必要書類の種類、免許の取扱区分、管理者・営業所の選定、ほかにも許可取得後の変更事項に関する手続、届出など、お困りのことがございましたら、お近くの行政書士にご相談ください。
運送事業の許可申請をお考えの方は、お気軽に当事務所にご連絡ください。
⇩
「行政書士千葉だいき事務所のホームページ」