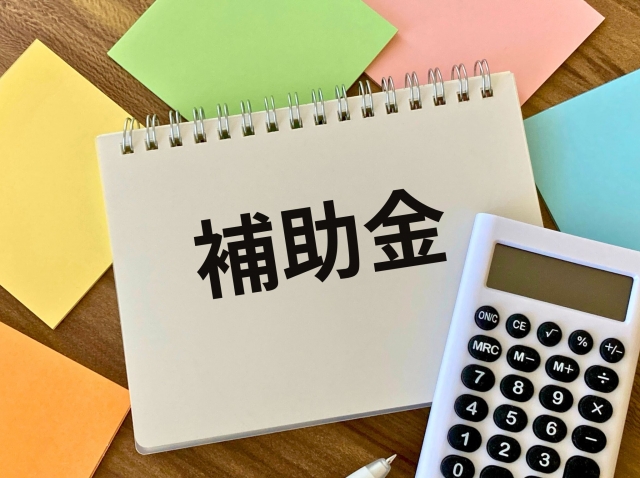小規模事業者持続化補助金とは
小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(物価高騰、賃上げ、インボイス制度の導入等)等に対応するために取り組む販路開拓等の取組の経費の一部を補助することにより、小規模事業者等の生産性向上と持続的発展を図ることを目的とします。小規模事業者等が自ら策定した持続的な経営に向けた経営計画に基づく、販路開拓等の取組や、販路開拓等と併せて行う業務効率化(生産性向上)の取組を支援するため、それに要する経費の一部を補助するものです。
(小規模事業者持続化補助金_第18回公募要領から抜粋・要約)
<小規模事業者持続化補助金(一般型 通常枠)第18回公募の概要>
補助金額:原則50万円(例外的に100万円・200万円・250万円になる場合あり)
補助率:原則2/3(賃金引上げ特例のうち赤字事業者は3/4)
対象者:小規模事業者(個人事業主も対象)
補助対象経費:機械装置等費、広報費、ウェブサイト関連費、展示会等出展費(オンラインによる展示会・商談会等 を含む)、旅費、新商品開発費、借料、委託・外注費
申請方法:電子申請システムでのみ受け付け(郵送での申請は一切受け付けません)
小規模事業者持続化補助金の活用を検討されている経営者の方々も多いと思います。そこで今回は、実際に申請する前の基礎知識について整理してみました。
①申請者の要件のポイントと注意点
「小規模事業者」であることが前提条件になります。業種ごとに従業員数で小規模事業者であるか否かを判断しています。
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く): 常時使用する従業員の数 5人以下
サービス業のうち宿泊業・娯楽業:常時使用する従業員の数 20人以下
製造業その他:常時使用する従業員の数 20人以下
ただし「製造業」については、本来は「製造業」に該当しないであろう事業者が、本補助金では「製造業」に該当する可能性がでてきているようです。
―――飲食店で調理技能用いて料理をその場で提供するのみであれば「サービス業」だが、調理技能を用いて流通性のある弁当、総菜、お土産等を作っていれば「製造業」に該当する、といったことになります。出版社・取次から仕入れた書籍をそのまま販売するのみであれば「商業・サービス業」だが、自社の知覚とノウハウをもとに、小説と小説内に登場する料理を提供する飲食店を掲載した案内雑誌を 「文字と舌で楽しみたいグルメセット」等として販売しているケースであれば「製造業(他者が生産したモノに新たな価値を付与している)」に該当する場合があるため、策定する補助事業が該当する業種となるか否かについては、専門家に確認してもらうと間違いないでしょう。
<申請不可の事業形態>
一般社団法人・一般財団法人・社会福祉法人・医療法人・医師・歯科医師・助産師・学校法人・宗教法人・任意団体・開業届を出していない創業予定者など
②電子申請(GビズID)のアカウント取得をしなければならない
公募要項に「申請には「GビズIDプライム」のアカウント取得が必要です。未取得の方は必ず事前に利用登録を行ってください。(GビズIDを取得 https://gbiz-id.go.jp/top/)」とあり、「申請は、電子申請システムでのみ受け付けます。郵送での申請は一切受け付けません。」といった申請ルールあります。また「第三者の支援者等に「GビズIDプライム」もしくは「GビズIDメンバー」のアカウント及びパスワードを開示することは、GビズIDの利用規約第11条に反する行為ですので、ご注意ください。」とあります。
―――この記載の意味するところは、「電子申請をする際の入力については、必ず申請者自身によって作業されなければならない」ということです。
このアカウントは無料で取得できます。一つめは「書類郵送申請」で、法人の場合は会社の印鑑証明書が、個人事業主であれば代表者個人の印鑑登録証明書が必要であり、発行まで一週間程度を要します。2つめは「オンライン申請」で、マイナンバーカードとスマートフォンで「GビズID」のアプリをインストールすることで、最短で即日発行されます。
③実現可能な計画でなければ補助金は獲得できない
<経営計画書>
事業者の過去から現在の振り返りを記載する
―――企業概要・顧客ニーズと市場の動向・商品(サービス)の強み弱み・経営方針・目標と今後のプラン、等を記述する。
<補助事業計画書>
現在から将来に向けて何をするかを記載する
―――販路開拓等の取り組み内容・補助事業を行うことで得られる効果、等を記述する。
<記述する際のキーワード>
「新規性」「独自性」:今までとは異なる新たな取り組みであり、競合他社がやっていない取り組みを行うこと
「創意工夫」:経営者の努力や綿密な事業計画があること
「実現可能性」:きちんと実現できる事業計画を立てること
④無資格・無責任な申請代行業者が存在する
小規模事業者持続化補助金の補助事業の採択を受けるためには、申請手段、採択獲得に向けたリソースを得る手間と時間を要するのみならず、「経営計画書」「事業計画書」などを作成する時間と労力を多忙な事業経営の合間に確保しなければなりません。さらに補助金事業として採択され、その補助金事業を完了した後にも、還付を受けるために多くの事務作業と手続が必要になります。多くの経営者の方が「補助金事業とは、こんなにも時間と手間を要するものなの?」「負担軽減のために代行業者を使ったほうがいいのかな?」とお感じになられるのではないでしょうか。
公募要項には、申請者の代行業者使用についての注意事項も記載されており、「事業計画の検討に際して第三者の支援を受ける場合には、提供するサービスの内容と乖離した「高額なアドバイス料金」を請求される業者等にご注意ください。」と記載されています。これは、申請の手続きを表面的に代行するだけで、申請完了の型を整えるだけで高額報酬を請求する業者等が後を絶たず、補助金事業の採択だけに拘り、申請者の意向に沿わない事業計画を作成して提出させる業者があることが背景となっています。
行政書士ではない者が「他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成すること(行政書士法第一条の二一部抜粋)」は、行政書士法の規定に抵触し得る「グレーな行為」になり得るのですが、それでも無資格で報酬を要求する業者が後を絶ちません。その事実を知らずに報酬の安さのみで「グレーな業者」を頼る経営者の方が一定数いらっしゃるのですが、今後(令和8年1月から)の法改正施行により、申請者(経営者)が「グレーな業者」を通じて補助金申請をした場合、その事実のみで「コンプライアンス欠如の事業者」「不正受給の事業者」として非難を受ける対象となります。「安物買いの銭失いだった!」「知らなかった!」と後悔しても悔やみきれない罠が潜んでいるのです。
合法的に行政書士に依頼しましょう
これからチャレンジしたい事業をすでに計画されている、もしくはこれから計画をお考えの経営者の方がいらっしゃいましたら、必ず行政書士にご相談ください。
―――行政書士は、計画されている事業内容に合致する補助金募集の選定と提案、すでにお持ちの「経営計画書」「事業計画書」等をブラッシングすることから、事業計画策定のサポート、採択後のサポートに至るまで、国家資格所持者である使命感を以て、トータルでサポートを承ることが可能です。
補助金活用での事業計画をお考えの方は、お気軽に当事務所にご連絡ください。