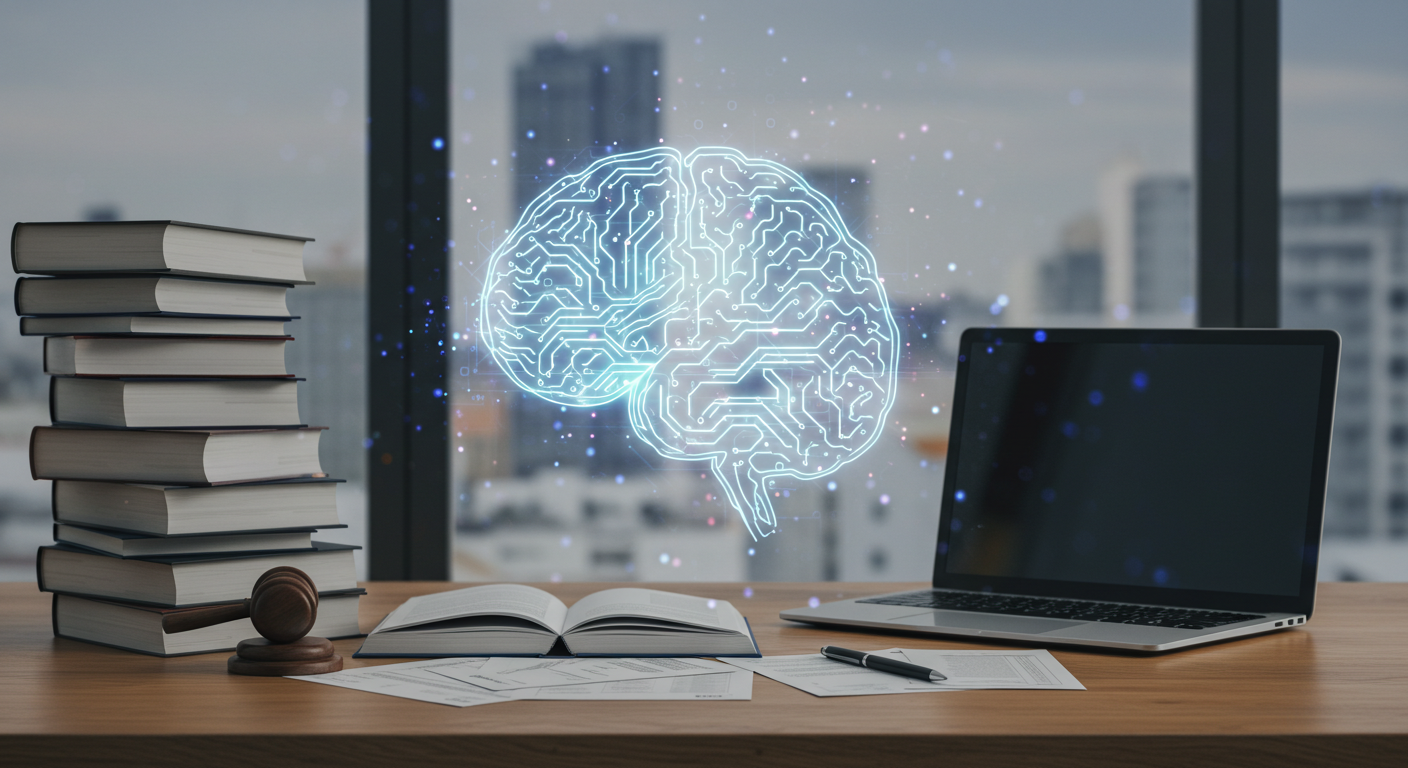「知的資産経営」とは、財務諸表などの数字に表れない企業の隠れた強みを「知的資産」として評価し、これを積極的に企業経営やビジネスに活用する経営手法をいいます。
「知的資産経営」導入のメリット
「知的資産経営」を導入し実践することにより、自社に潜在する強みを認識し、経営資源として活用することで企業経営力の強化を図ることができます。たとえば、以下のような成果をもたらす可能性があります。
・「知的資産の見える化」は、経営課題の明確化にも寄与するため、効果的な事業計画作成の指針になる
・「知的資産の見える化」を進めること自体が、従業員教育の一環となる。(経営理念の理解、コンプライアンスの浸透、人財の育成・能力の向上)
・「知的資産の見える化」によって、既存従業員のモチベーションが向上することにより、優秀な人財の安定確保が見込める
・「知的資産経営報告書」を作成することで、融資、資金調達、助成金等を申請する際には高評価ポイントの獲得を期待できる
・「知的資産経営報告書」が、事業承継のためのツールになり得る(後継者育成、資産承継など)
・「知的資産経営報告書」を公表した際の効果として、取引の拡大が見込める
「知的資産経営報告書」の作成について
知的資産経営報告書は、財務諸表とは異なり、記載方法に関する明確なルールはなく、さらに記載される項目は無形であるが故に、記載者の表現力によって信頼性や共感度に差が生じます。また、評価者である第三者の知的資産に対する認識の違いによって、評価に大きな差が生じること、また、無形資産は所有者自身や所有者の用い方によっても価値が変化してしまうこともあります。
このため、知的資産経営報告書を作成する際には、無形資産の存在と業績の関連性、今後の活用方針などを「一連の流れ」で示すことによって、第三者による無形資産の評価が容易になるように注力します。「知的資産が事業に対してどのように影響を与えているのか」「今後どのような事業へ展開可能なのか」といったことを、知的資産を「事業の流れ」のなかで捉えて表現する方法が一般的となっています。
知的資産を流れで捉える
知的資産を「事業の流れ」のなかで捉えて表現する方法ですが、それには事業の流れのなかに知的資産がどのように関係しているのかを見せてゆく必要があります。
そこで、一定のフレーム(型)で見せることで、他社比較も容易にして、読み手の理解が進むような工夫を施します。しかしながら、フレームを用いても知的資産の完全な定量化はできませんから、有形資産を数量的に示せる財務諸表のように「完全な比較」をすることの難しさは残ってしまいます。それでも企業の競争力の源泉となっている知的資産情報を加えて企業評価をすることについて、その有益性が疑われることは決してないでしょう。
セグメント分析
通常、企業の一連の事業活動は、会社の基本となる「①経営理念や方針」のもと、会社の内外の体制整備に向けた「②マネジメント」を経て、「③技術・ノウハウ」やネットワークを構築することで、高い性能やシェアの「④製品・サービス」を提供し、その結果が業績に表れるという流れになっています。
上記の①~④ように「4つのセグメント」に分類して知的資産の動的な価値を事業活動の流れに沿って「図式化=見える化」して捉えることで、知的資産と業績の関係を明らかにしてゆきます。一連の流れの最終部分である「④製品・サービス」のセグメントから、「①経営理念・方針」のセグメントに向けて、事業の流れを遡るように見てゆくことがポイントであり、隣り合うセグメントの各要素の一つ一つの因果関係を丁寧に分析してゆき、「動的な価値としての知的資産」を見つけてゆく作業になります。
「知的資産経営報告書」の作成支援
知的資産とは、財務諸表に現れない、金銭価値で表わせない評価対象です。これを見える形で表現したものが「知的資産経営報告書」です。その作成にあたって、抽出した知的資産の定量評価や、KPI(重要業績指標)などの信頼性・ 信憑性をいかに確保するかが問われます。
「知的資産経営報告書」は、企業内外とのコミュニケーションツールとしてだけでなく、企業マネジメントツールとして活用できるため、本来は企業自らが作成することが望ましいものです。しかし、企業内部者間のマンパワー等によって、報告書の記載内容に忖度、歪みが発生したりすることもあり、外部の支援者が作成せざるを得ない場合が多いことも事実です。そこで、知的資産経営報告書を作成するに当たって、行政書士のような支援者(外部専門家)が必要となってきます。
「行政書士千葉だいき事務所」では、申請者の方の同意のもとで、知的資産の洗い出しのサポートから、得られた非財務情報を分かりやすい表現でまとめるサポートにも努めております。
「知的資産経営」導入をお考えの方は、お気軽に当事務所にご連絡ください。
⇩
「行政書士千葉だいき事務所のホームページ」